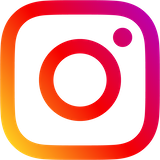はじめに
皆さんは、普段の食事をどれくらい意識されていますか?
「体重を減らしたい」「体型を維持したい」という方は気をつけているかもしれません。
一方で、あまり意識せず「好きなものを食べているだけ」という方も多いでしょう。
もちろん、ストレスを溜めないために好きなものを食べることも大切です。
しかし、全く意識をしないでいると健康を崩す原因となり、生活習慣病へとつながるリスクもあります。
そこで今回は、「健康と食事の関係」について、医学的な根拠を交えながら解説していきます。
食事の重要性
まず大切なのは、「食事は健康を支える基本」ということです。
実際に、生活習慣病の多くは食生活の乱れが原因です。
- 高血圧 → 塩分の摂りすぎ
- 脂質異常症 → 脂質(特に悪玉コレステロール)の過剰摂取
- 糖尿病 → 糖分や炭水化物の摂りすぎ
特に日本人は「塩分過多」になりやすい傾向があります。
厚生労働省の調査では、日本人の1日の平均食塩摂取量は 約10g。しかし、世界保健機関(WHO)が推奨する基準は 1日5g未満です。
つまり、日本人は塩分を必要量の約2倍摂っていることになります。
そのため、食事を意識するかどうかで将来の健康は大きく変わるといえるのです。
理想的な食事とは?
次に、どんな食事が理想的なのかを見ていきましょう。
人の体は「五大栄養素」で成り立っています。
- 炭水化物 → エネルギー源(ご飯・パン・麺類など)
- タンパク質 → 筋肉や臓器の材料(魚・肉・大豆製品など)
- 脂質 → 細胞やホルモンを作る(油・ナッツ・乳製品など)
- ビタミン → 体調の調整(野菜・果物など)
- ミネラル → 骨や代謝に必須(カルシウム・鉄・亜鉛など)
どれも欠かせない栄養素であり、バランス良く摂ることが健康維持に不可欠です。
反対に、どれかが不足・過剰になると体調不良や病気の原因になります。
バランスをとる工夫
とはいえ、「五大栄養素を意識してください」と言われても難しいですよね。
そこで役立つのが、「主食・主菜・副菜」をそろえることです。

例)
- 主食 → ご飯(炭水化物)
- 主菜 → 鮭の塩焼き(タンパク質)
- 副菜 → ほうれん草のお浸し(ビタミン・ミネラル)
この組み合わせを意識するだけで、自然と栄養バランスが整いやすくなります。
さらに、調理法を工夫して塩分を控えめにすることで生活習慣病の予防効果も期待できるのです。
食事と健康寿命
また、近年の研究では「食事の質」が健康寿命に直結することが明らかになっています。
つまり、栄養バランスのとれた食事を心がける人は、生活習慣病や心疾患のリスクが下がり、長く元気に過ごせる可能性が高まります。
一方で、偏った食事を続けると体に負担がかかり、病気のリスクを高める結果につながります。
したがって、「好きなものを食べる楽しみ」と「健康的な食事の意識」の両立が重要なのです。
まとめ
今回は「健康と食事」について解説しました。
- 食事は生活習慣病の大きな要因になる
- 五大栄養素をバランスよく摂ることが健康の基本
- 「主食・主菜・副菜」を意識すれば自然と整う
- 塩分を控えることが生活習慣病予防に効果的
好きなものを食べられる生活は幸せです☺️
ただし、その幸せを長く続けるためには「バランスのとれた食事」を意識することが大切です。
今日から少しずつでも食事を工夫して、未来の健康を守っていきましょう。
前回の投稿はこちら!
https://ark-conditioning.com/news/3035
Instagramでは様々な情報を投稿しているのでそちらもご覧ください!